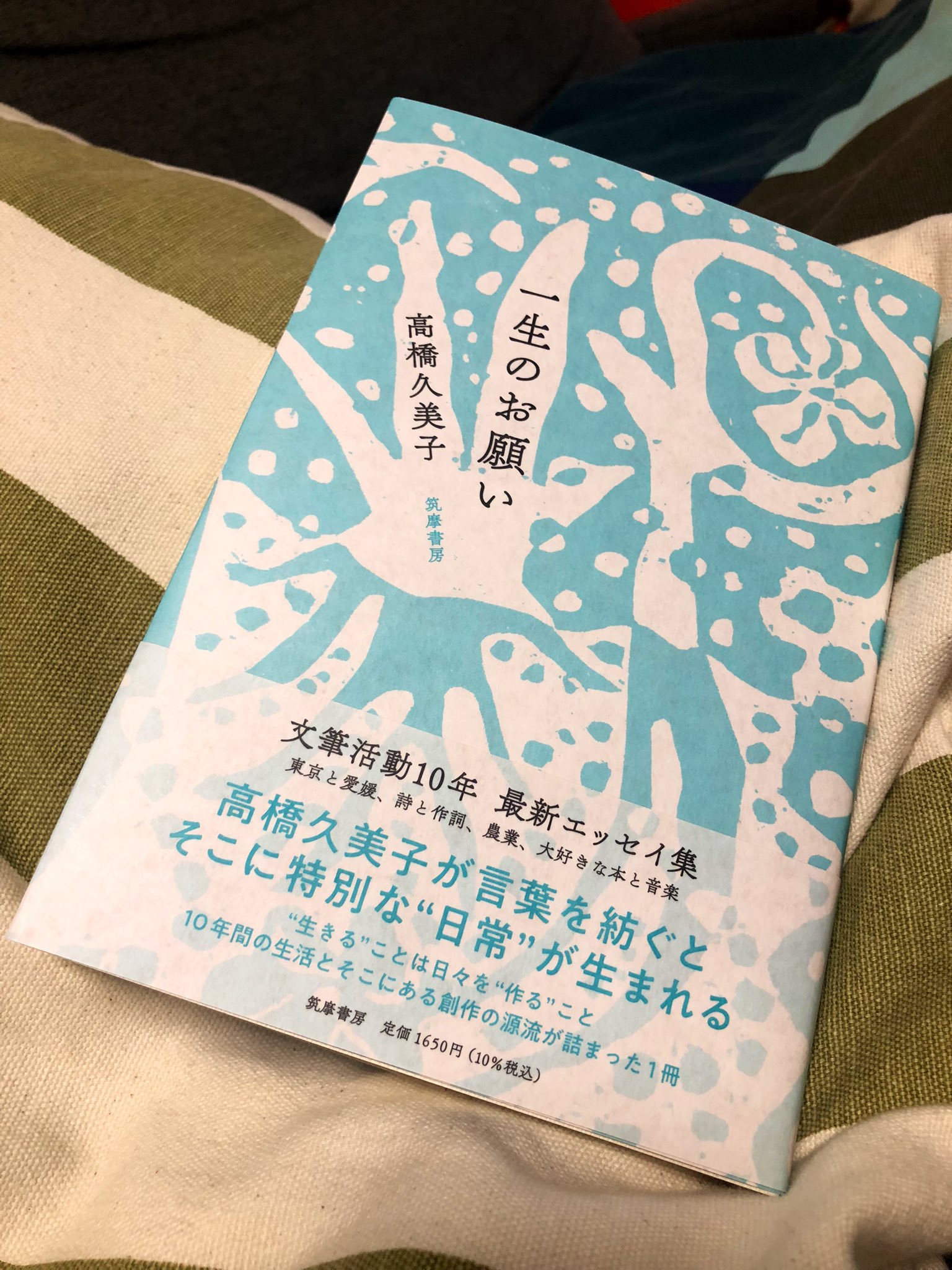高橋久美子『一生のお願い』(筑摩書房)を読みました。
ブックレビューの前に、少し思い出話から。高橋さんとは、イベントで何度かご一緒させていただいたことがある。高橋さんはなんというか、とにかく人を萎縮させない佇まいを持っている。当然、わたしのほうは高橋さんのことを高校生ぐらいのときから一方的に知っていたわけで、お会いしてごあいさつするというのでドキドキしていたら、ちょっと拍子抜けしたくらいだった。あれっ、わたし、この方と前にもお会いしたことがあったのだっけ……? そして、なんだかすでにちょっと親しくなっていたのだっけ……? というような錯覚を、高橋さんの存在は起こさせる(なんだかナンパ師みたいなせりふでいやだが、でも、本当にそんなように思うのだ)。そのあとにパフォーマンスを拝見したのだが、そっちもすさまじかった。いろいろなイベントに出ていると、よく、楽屋では親しみやすかった人が舞台に乗ると別人のようになって、すごいなあ、と思うことがあるけれど、高橋さんの場合は全く逆だった。高橋さんはあの、ぽやんとした(すみません)、人を萎縮させないどころかそれを通り越して油断させてしまうような存在のまま、すらっと舞台の上に立ってしまう。声にしてもそれは同じで、話す声と、歌う声と、詩を朗読する声とが、すべて同じ線の上でつながっている。それがたまらなくかっこよかった。
『一生のお願い』はエッセイ集である。どのエッセイを読んでいても、その、やさしくて、こちらの肩の力まで抜いてしまうような、それでいてぴんと張った、高橋さんの声がする。自然な言葉で、なにげない日常を書いているようでありながら、暮らしというものの芯のほうへ迫っていこうとする。食べること。家に帰ってくること。知らない人と出会うこと、またそれと全く同じように親戚や、旧い友だちや、家族と出会うこと。そのすべてに対して、高橋さんは真剣である。真剣でありながら、ちょっと焦点があっていないような、ふしぎな距離のとりかたをする。本の中には書くことやお仕事について書かれたエッセイもたくさんあり、それらを読んでいると、これは書いているからこそできる距離ではなかろうか、と思う。いつでもアイデアを、言葉を探しているまなざしが、いたずらっぽく日常を観察する。
わたしには、日常や暮らしというものが、ふつう剣呑に思えてしかたない。ちょっとすると濁流のように自分を飲みこみ、なにかもっと大きなシステムのようなものへ巻き込んでしまう、おそろしいやつだと思っている。けれども高橋さんのエッセイを読んでいると、自分の暮らしもそんなに悪くない、めんどくさいけれどもチャーミングで、ときどききらっと光ってみせるものに思えてくる。きっと、高橋さんの前に立たされると、あのおそろしい暮らしというやつも骨抜きにされてしまうんだろう。
それから、ところどころに見える、流動体のような軽さに惹かれる。東京と愛媛との二拠点生活にしてもそう、詩・エッセイ・小説・作詞・ライブ出演……というお仕事の幅広さにしてもそう、高橋さんの日々には独特の軽みがある。中でもおもしろかったのは、愛媛の実家を改装するとき、住み込みの大工さんたちと生活した日々を描く「そうだ、長崎に行こう」。長崎からやってきた最大七人の大工さんたちは座敷に寝泊まりし、お母さんが作ったご飯を昼も夜も一緒に食べる。ベトナムから来たザンくんをはじめとする大工さんの弟子たちの紹介もおかしい。棟梁の島田さんからふるさとの祭りに誘われれば、タイトルの通りひょっと長崎まで行き、祭りの踊り子までしてしまう。そして高橋さんは愛媛の家に帰り、また東京の家にも帰ってくる。そのどちらもが「帰る」であるのだという。
「家」というものは、安全な場所である一方、中にいる人を縛りつけたり、外にいる人を疎外したりする一面を持っている。けれども高橋さんの家は、大工さんたちの出入りを風のように受け入れ、高橋さん自身の出入りも制限しない。どちらにとっても開かれている。読んでいて、関係のないわたしも、胸がすくような思いがする。高橋さんはまた、人が自分をなんと呼ぶかに敏感に反応する。セールスマンに「奥さん」と呼ばれて青ざめ、甥っ子姪っ子たちからの「びーこさん」という呼び名に、自分と彼らとの唯一無二な関係を重ねる。肩書きについても何度も考える。
康雄くんが「高橋久美子(作家・作詞家)だけど、久美子さんは何通りもの人生を歩いているから、『高橋久美子(高橋久美子)』ですよね」と言った。さすが、うまいこと言いよるわーと思った。(「高橋久美子(高橋久美子)」64頁)
詩人というと変わり者と思われがちなので、肩書きは「作家・作詞家」ということにしている。(中略)「作家」というと、何か賢げな感じがする。「作詞家」というと秋元康みたいに売れっ子な感じがする。でも「詩人」=「変人」と変換されるらしい。(「肩書」182頁)
思春期の葛藤が私の土台になっていることは確かだ。それを救ってくれたのは詩だしこれからもきっとそうだから、私はやっぱり詩人なのだ。(同上、183頁)
高橋さんの、家に対する軽やかさと、呼ばれ方や肩書きに対する真剣さは、やはりどこかで関係しあっているように思える。家が開かれているためには、ただ柔軟なだけではだめで、ある種の強靭さが必要になる。そうでないと長く開かれつづけることはできず、いずれ崩壊してしまう。それと同じように、軽やかにあちこちを行き来する高橋さんもまた、やわらかでありながら、強靭な部分を持っているのだろう。「奥さん」という呼びかけを拒み、子どもたちに「びーこさん」と呼ばれ、「作家・作詞家」でありながら根底では「詩人」である高橋さん。そこに、高橋さんのあのぽやんとした魅力のひみつがあるのでは、と、わたしは勝手に推測している(個人的にはまた、土台にあるのが「詩人」という肩書であることに背中を押されたような思いだった)。
居場所を見つけること、自分が何者であるかわかること。ついつい難しいことだと思ってしまいそうになるけれど、高橋さんのエッセイを読んでいると、そういう問題ともこんなに軽やかに付き合うことができるのか、と驚く。日常をおそれるのでも、逆にただ肯定するのでもなく、ちょっと離れて見つめてみたくなる。きっと案外、同じ線の上に、重要な問題が隠れているのだ。